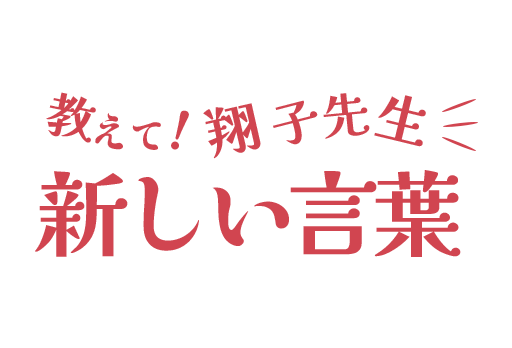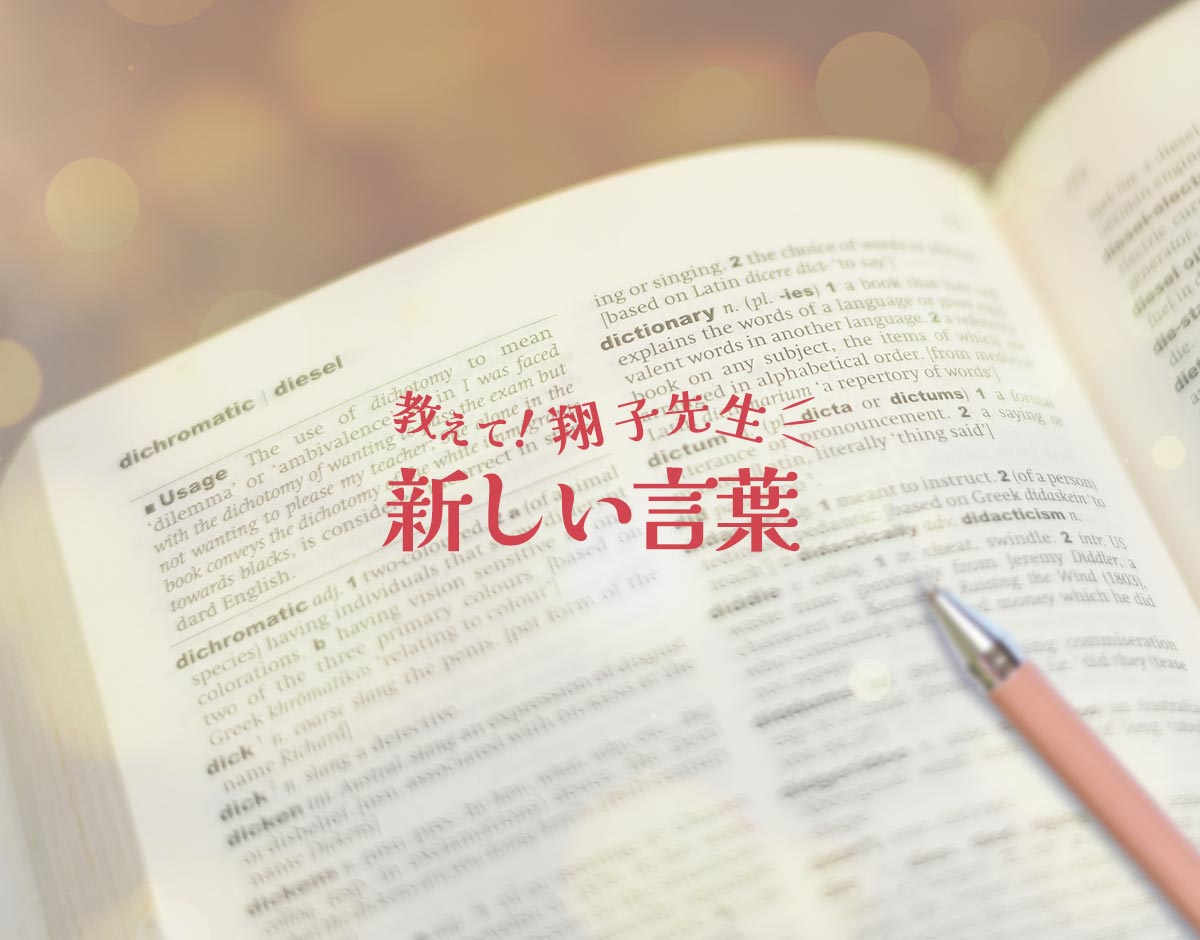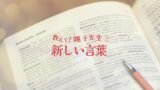学校では絵画、会社では資料、家庭では料理など、ほとんどの人が新しいものをつくった経験があるでしょう。
そのときの経験は「作る」と「創る」と「造る」のどれに該当するか分かりますか。
何をつくったかによって、使う漢字は違ってきます。
この記事では、「作る」と「創る」と「造る」の違いを分かりやすく説明していきます。
「作る」とは?
「作る」とは?
こしらえる、栽培、耕作するという意味です。
具象的な小規模なものや抽象的なものを「作る」という意味で広く使います。
「作る」の例文
「作る」の例文
人が生み出すもののほとんどは「作る」に該当し、非常に多く使うことになるでしょう。
・『私は子どもを作りたいので、今日からお酒を飲みません。』
子どもも「作る」を使用します。
友達を「作る」も同様です。
・『あなたは泣きたいけれど、無理して笑顔を作っていますね。』
表面的に取り繕うときも「作る」で表します。
若作りも同じになります。
「創る」とは?
「創る」とは?
新しいものを初めてつくり出すという意味です。
新しいものであれば、抽象的でも具象的でも使えます。
芸術作品や文化に使うことが多いでしょう。
しかし、常用漢字表には「つくる」の訓読みがないため、公的な文書には使用できません。
そのため、公的なものには「作る」「造る」のどちらかに当てはまる方を使うことになり、「創る」の漢字でなければならない文は存在しません。
「創る」の例文
「創る」の例文
「創る」は新しいものであることを強調したいときに使うと効果的でしょう。
・『私はあなたと仲直りして思いを伝えるために、新しい歌を創りました。』
新しい歌をわざわざ創ったと強調したいときに使うと、努力したことが相手に少し伝わるでしょう。
・『彼はフィンランドの教育を取り入れた学校を創りました。』
学校などは創立するというため、「創る」を使うことが多くなります。
公的文書の場合は、この文のように理想の学校という抽象的な意味であれば「作る」になり、建造物として会社がこの場所に建てるという具象的な意味であれば「造る」に該当します。
「造る」とは?
「造る」とは?
大規模な物や具象的な物を工業的にこしらえるという意味です。
建造、造船、醸造など、言い換えることが可能になる場合が多くなります。
組織、制度、仕組みなどを新しく生み出すときにも使います。
「造る」の例文
「造る」の例文
大規模な物に使うため、一人ではできないことが多くなります。
・『私の会社は、このタワーを造りました。』
ここで「作る」の方の漢字を使ってしまうと、図画工作の小さなタワーだと思われてしまいます。
・『このお酒はアメリカのワシントン州で造られました。』
お酒は小規模の物と思われるかもしれませんが、一人の手によって、つくられたとは考えにくいでしょう。
機械で製造して造られているため、大規模と判断し、「造る」という漢字が該当します。
「作る」と「創る」と「造る」の違い
「作る」と「創る」と「造る」の違い
「作る」と「創る」は一人でもつくることが可能で、具象的な小規模なものや抽象的なものを生み出したときに使い、「造る」は大人数でつくり、大規模で具象的な物にだけ使います。
「創る」は新しいものを生み出すときに使い、公的な文書には使えないため、「作る」か「造る」に言い換えることが可能です。
まとめ
まとめ
つくるという行いは漢字で分類でき、間違った使い方をすると勘違いされる場合があるでしょう。
また「創る」を上手に使えば、新しいものであることが一目で分かり、相手に与える印象が変わります。
そのときに合ったふさわしい漢字を使い、分かりやすい文章を書くように意識しましょう。